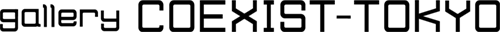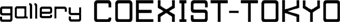作為と不作為と ―井上実の制作
井上実の制作には、作為と不作為が意外なあり方で交錯している。
彼は近年もっぱら草むらを描いている。玉川上水の中流傍らにある住まいの周囲には、武蔵野台地の自然がよく残されており、取材するのはそこここに見出だされる何ということのない草深い空地である。散歩の最中にそこから気に入った一画を撮影し、それが題材となる。どんなアングルで切り取るかは、作家がどのような絵画を描きたいかという美意識に深く関わっているはずだ。
草むらの画像のプリントアウトを前に描き始めると、それは私たちが通例と考えている方法とは大きく異なっている。画像は幾分拡大されてキャンバスに転写される。草木のディテールや重なりが正確に鉛筆で描き起こされ、そこにごく薄く溶かれた油絵具で色彩が置かれていく。実景は全くと言って良い程改変されない。画像で判別できる限り、草の一本、葉の一枚まで正確に写し取られている。そんなところは誤魔化しても観る方には判らないだろうにと思うが、可能な限り作為を排するのが制作上のポリシーなのだ。
大きなサイズのキャンバスの場合、広げることができないので、巻いたキャンバスを床に置き、端から開けて描いていく。その間、作品の全貌がどのようになるのか、自分でも把握されていないようである。作品の行先をコントロールすることも放棄している。出来上がったうえで作品の全体を観て、細部を調整することもないらしい。端から描いて、反対の端まできたら終わり、といった感じなのだ。制作をコントロールしようとすると上手くゆかず、かえって失敗するとこれまでの数々の経験から信じているのだという。
作為を排して行方のわからぬまま描き、出来上がった画面を受け容れるというと、制作主体の意志をどう考えるべきなのかという疑問も生じる。自働書記の一種とみるべきなのだろうか。絵画の平面性を前提として、全体と細部との関係を意識的に制御しようとするのが、近代以降の絵画制作に通底する認識のはずだが、それを敢えて放棄しているようにもみえる。もちろん全貌の見えぬまま描き進めるのは、自身にとっても苦痛な作業なのだが、必要な結果を得るために、作家はそれを肯定的に捉えようとしている。
「描き終えるその日まで、どうやって描いたらいいのかわからないままでした。(中略) どうやったらいいかわからない事、先がわからない事に挑むとき、その人の本質が出るような気がしますので、そういう意味では、理想の状態ともいえるのです。」(作家のブログから)
では作家が敢えて作為を排除することによって得ようとしている、「本質」とは何なのだろうか。このようなユニークな方法によって出来上がる成果を、作家自身が良しとしているならば、その答えは作品のなかに見出される他ない。画面が持っている独特な質こそが、苦行のような制作の末に、作家が実現しようとしていることのように筆者には思える。
一木一草を正確に描きながら、細密に描かれた写真のようなリアルを求めているのでないことは明らかだ。画面は地面とその上を這う草葉によってくまなく満たされ、浅い奥行きをもったオールオーバーな空間が形成されている。鉛筆で描かれた輪郭は、彩色の際に消されてしまう。規則正しいのではないのだが、ほぼ同じ大きさに分節された筆触によって、画面全体に振動するようなリズムと、均質な強度が与えられている。陰影の描写はなされない。水彩のように薄い絵具の、繊細な色彩の輝き。筆触は重なりあうというより、その隙間からキャンバスの白が覗くように置かれており、それが背後から射す光の粒子のような効果を与えている。
理解に苦しむのが、高度に統御されたかにみえるこのような画面が、作家の意図的な不作為の結果として現れているということなのである。意識化され得ない、身体化された技術ということなのか。それには相当な研鑽が必要なはずだ。しかし作為を禁じることでそれが滲み出すことを、作家が経験的に知っているということなのかもしれない。
三菱一号館美術館
学芸グループ長 野口玲一
■イベント情報
オープニングレセプション
日 付 : 11月12日(土)
時 間 : 18時~ (約1時間30分)
ギャラリートーク
12月3日(土)18時から、トークゲストに野口玲一 氏(三菱一号館美術館 学芸グループ長)をお迎えして、トークイベントを行います。お気軽に、ご来廊ください。

画像(上から)
・「ひなげし」 油彩・キャンバス 2015 年 162×194cm 撮影:柳場大
・展示風景 「井上実展」 art space kimura ASK? 2015 年 撮影:柳場大